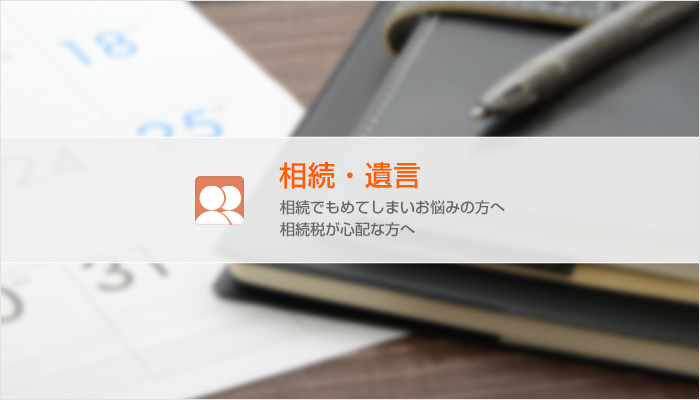
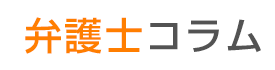
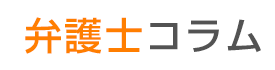
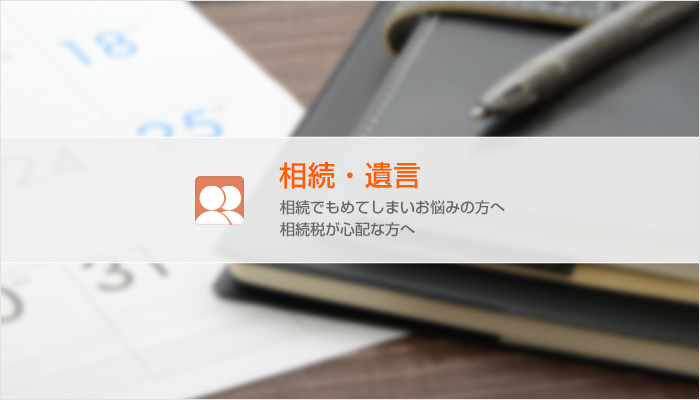
先日、姉Aが亡くなりました。相続人は、姉Aの兄弟である兄Xと弟である私Yのみです。姉Aの遺産は、自宅土地建物、預貯金で総額2000万円程でした。
葬儀の後、亡くなった姉Aが、「自分の財産を全て兄Xに相続させる」という内容の公正証書遺言を作成していたことが分かりました。
しかし、姉Aは、遺言を作成したときには、既にアルツハイマー型認知症の診断を受けていました。公証役場へ連れて行く等、兄Xの主導により公正証書遺言を作成したようですが、公証人にはアルツハイマー型認知症だと事前に伝えられていなかったそうです。私は、兄Xが認知症になってしまった姉Aを言いくるめ、自分に有利な遺言を作らせたのではないかと考えています。
確かに、姉Aが認知症になってからは姉の家になかなか通い詰めることはできていませんでしたが、介護に来てくれているヘルパーの方の話では、姉Aは、亡くなる数カ月前に「弟Yは偶に来るけれど良くしてくれている」と言っていたそうです。姉Aと喧嘩したということもありませんし、兄弟のことを平等に扱ってくれていました。全ての財産を兄Xへ相続させるという遺言は釈然としません。
今後、どのように対応していけばよいでしょうか。
本件では、姉Aがアルツハイマー型認知症の診断を受けていることから、遺言能力を欠いていた可能性があります。遺言能力とは遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識し判断することのできる能力です。遺言能力がなければ当該遺言は無効となりますので、遺言時に遺言能力があったのかが問題となります(民法963条)。
姉Aは認知症を患っていたとのことですが、認知症の方が必ず遺言の有効性が否定されるというわけではありません。遺言の有効性が認められるには、次の⑴~⑷がポイントと考えられます。
(1) 遺言者の精神的疾患の存否、内容、程度
・認知症とは、認知機能障害のために生活に支障をきたした状態のことをいいます。同じ認知症 であったとしても、全般性の認知症状を呈するとされるアルツハイマー型か、まだらの認知症状を呈するに留まるとされる血管性型かの違いは着目する事情の一つです。
・他の要素との兼ね合いもありますが、認知症の重症度が軽度である場合は遺言能力ありとされる可能性はあり、中程度から重度である場合は遺言能力なしとされる可能性が高まる事情と考えられます。
(2) 遺言内容形成の難易の程度
・遺言内容は金額的2000万円と大きいものの、全て兄Xに相続させるという内容であるため、簡単な内容であるとも考えられます。
(3) 遺言内容の自然性・合理性・公平性の程度
・本件では、姉Aの生前の意思と合致しているかは不明です。
・しかし、姉Aが生前、兄弟を平等に扱っていたこと、弟Yは姉Aと特に喧嘩して不仲になったということもないこと、遺言が兄Xへ全て相続させるという内容になっていることは、遺言能力が無かった方向に傾く事情であると考えられます。
・また、兄Xが主導して公正証書遺言を作成したということから、その意見に迎合してしまっていた可能性があります。
(4) 遺言作成前後の言動や経緯
・本件では、姉Aは公証役場に赴いて公正証書遺言を作成していますが、公証人にはアルツハイマー型認知症だと事前に伝えられていなかったようです。しかし、通常、公証人は遺言能力に疑義がないか確認しますので、その時の姉Aの応答がどのようなものだったかは問題となります。質問に対し、単に「はい」とか「うん」といった応答しかできていないと、疑義が生じやすいといえます。
・ヘルパーの方とのコミュニケーションがどのようなものだったかも問題となります。自己の置かれた状況を踏まえたコミュニケーションが取れている場合は、遺言能力がある方向に傾く事情といえます。
まず、上記のポイントを参考に、診断書や介護記録、公証人の証言等を集めつつ、兄Xに対し、遺言の無効を前提に遺産分割の交渉をすることが考えられます。しかし、兄Xが遺言の作成に積極的に関わっていたのだとすれば、交渉に応じない可能性が高いです。
交渉が決裂した場合は、遺言無効確認訴訟を提起し、遺言が無効であると認められれば、兄Xとの間で遺産分割協議書を作成していくことになります。
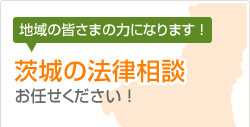
対応エリア
茨城県全域(石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市、守谷市、結城市、龍ケ崎市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都など、関東地域
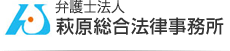
![]()